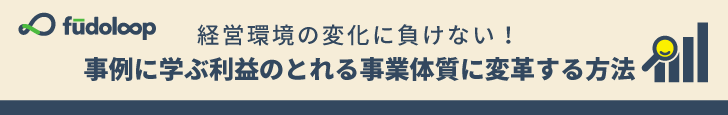第3章 自社の問題に対し行動を起こした沼津中央青果様の取り組み
前章では沼津中央青果様が気づいた自社の問題とそこから設定した課題についてお伝えしてきました。この章では、沼津中央青果様が気づいた問題・課題をどう解決しようと試みたかについて紹介していきます。
3-1.取り組み1:思い切って競売を廃止、「提案型営業」を実践
STEP1:提案型営業の導入
買いたたきが発生しているという問題に対して、沼津中央青果様が取り組む必要があると考えたのが販売形態の変革でした。その考えにもとづいて実行したのが競売の廃止です。量販店などの買い手の働き方改革によって競売に来なくなったことを受けて、これまで当日朝の競売によって販売額を決定する市場の仕組みだったものを、競売を無くして前日までに翌日の受注を完了させる「提案型営業」の販売形態に変更したそうです。「提案型営業」は、量販店の市場に並ぶ前日の朝に、翌日の出荷予測情報をLINEや電話で地場産品担当営業が入手し取りまとめて、午後には量販店に提案書をFAXで送付します。夕方までに買い手からの受注がおおよそ出そろうことで、当日の競売を撤廃する動きを取るというものです。
この舵切りによって、今まで朝の競売で並んでいた野菜の行先の大半が決まることになり、 朝競売にやってきた小規模の小売業者からの買いたたきをされずに販売ができる状態に戻せたということです。
遠藤様はこの取り組みについて「事前に出荷情報が分かれば、我々も強気で小売さんへ販売ができるようになります。すると競売の必要がなくなり、競売がなくなると買いたたきもなくなります。それが買いたたきをなくすベストな手段だったと思っています。」と語っています。

STEP2:fudoloopの導入
ただ、提案型営業の実践は、最初からすべて上手くいったわけではありません。
取り組みをはじめた当初は、生産者への翌日の出荷量のヒアリングは電話やLINEで個別に行い、その後集計していたためどうしても大きな手間が発生していました。
生産者1人との電話でのコミュニケーションには3〜4時間程度かかることも。そもそも電話が繋がらないタイミングも多々あり、かなり非効率でストレスを抱えるものでした。
そこで、業務の効率化の実現のために市場・青果卸の業務改善アプリであるfudoloopを導入しました。これにより、生産者には出荷の前日午前中までに、自分のスマホからfudoloopで出荷予定量を入力してもらうだけでよくなりました。出荷予定量のデータが自動でたまっていくので、営業担当が電話やLINEでのアナログなヒアリングをする必要がなくなり、業務に時間がかからなくなったそうです。
出荷予定量だけではなく仕切データ等も蓄積されていくため、たまったデータを組織内で簡単に共有できる点も良い点だったと遠藤様はいいます。fudoloopの導入で、提案型営業に効率よく取り組むための基盤を整えることができました。

その他、競売廃止のためにしたこと
沼津中央青果様は販売形態の見直しにあたって、小売業者との間だけでなく、生産者との関係においても変革を実施しました。
まず、販売額の最低ラインを守り、高く売らずとも常に利益が出るような販売額の決定を行うように方針を変更しました。これにより、生産者に対して安定して利益の出る販売を行う市場だという安心感を与えることができました。同時に、安定した価格で販売をするためには安定した品質の実現も必要です。遠藤様は、品質に不安がある野菜を持ってくる生産者には電話をかけたり、時には直接見本の野菜を持って訪問し、「こんなんじゃだめだぞ」と伝えることもあるそうです。
生産者にとっては耳の痛い指摘であっても、よい質の青果を作ってきたらしっかり生産者の利益が出る価格で購入するようにしたことで「あの市場に卸せばちゃんと利益が出せる」と信頼してくれるようになり、沼津中央青果様の認識も定着していったそうです。
取り組み1についてのまとめ
沼津中央青果様では買いたたき問題を解決するために、自分たちの販売形態の変革を課題と設定しました。具体的な取り組みとして、買い手とは競売を廃止し前日までに受注を行う「提案型営業」で、生産者とは関係性を強化することで「青果の価格を守る代わりに、質を担保する」という新しい形で市場の価格形成機能を取り戻すことができました。
ここがポイント
・前日に量販店からの注文を受け付ける体制に合わせて「提案型営業」を導入
・生産者からの入荷量把握業務を効率化するためにfudoloopを導入・活用
・買いたたきをなくすために、「競売」をなくす
以上
※fudoloopメールマガジン(掲載日:2023年8月25日)
※本事例中に記載の肩書きや数値、社名、固有名詞および製品名等は、閲覧時に変更されている可能性があることをご了承ください。